- マーケティングDXとは
- マーケティングDXとデジタルマーケティングの違い
- マーケティングDXを推進するメリット
- マーケティング業務が効率化し、生産性が向上する
- データに基づいた客観的な判断ができる
- 顧客体験が向上する
- 新たなサービスやビジネスモデルの構築につながる
- マーケティングDX推進の課題
- 人材不足
- マーケティング業務の複雑化
- マーケティングDXを成功させるポイント
- 経営層によるコミットメント
- ミッション/目的の浸透
- 顧客視点での顧客体験の向上
- 外部パートナーとの連携
- 効率的に社内で始めることができるツールを利用
- マーケティングDXの成功事例
- 江崎グリコ株式会社
- JTB
- 日本コカ・コーラ
- U.S.M.H
- まとめ
マーケティングDXとは

マーケティングDXとは、市場調査や商品開発、広告宣伝、流通チャネルの設計など、様々なマーケティングの過程においてデジタル技術を用いて、業務変革を行うことです。
そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用してビジネス、組織や企業そのものを変革し、顧客に新たな価値を提供することを指します。
情報処理推進機構による「DX」の定義は以下の通りです。
"企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること"
2018年、経済産業省は今後日本においてDXが進まない場合、2025年以降に年間最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があるとのレポートを発表しました。
また、コロナ禍により世の中が一気にデジタル化したことを背景に、現在国内でDX推進の機運が高まっています。
マーケティングDXとデジタルマーケティングの違い
マーケティングDXと混同されがちな言葉として、「デジタルマーケティング」があります。デジタルマーケティングとは、インターネットやITなどデジタル技術を使ったマーケティング”手法”のことです。
WebサイトやSNS、アプリなどのITツールの活用はもちろん、リアル店舗への来店や購入などのデータ活用も含まれます。
一方、マーケティングDXは「デジタル技術を使うことで業務を変革すること」を指しています。デジタルマーケティングはあくまでも「マーケティング手法のひとつ」であり、ビジネスそのものの変革を目的としているわけではありません。
つまり、デジタルマーケティングとマーケティングDXは、手段と目的のような関係性と言えるでしょう。
マーケティングDXを推進するメリット
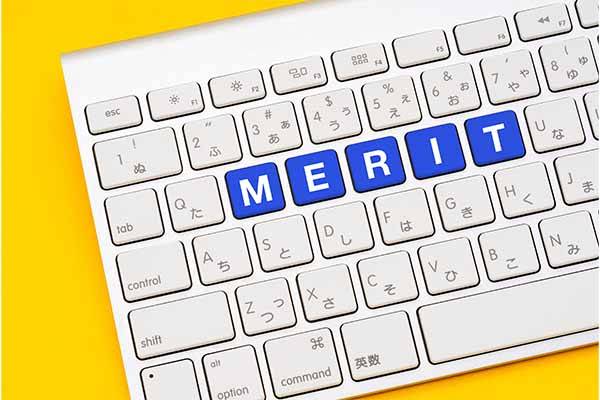
マーケティングDXを推進することで、これまで人的に行っていた業務が自動化され業務効率が上がるだけでなく、それにより顧客体験が向上するというメリットを得られます。
マーケティング業務が効率化し、生産性が向上する
マーケティングDXを推進することは、業務の効率化と生産性の向上につながります。マーケターの業務は多岐に渡ります。すべてを人の手で行うのではなく、デジタル化でできる業務は自動化し、思考や判断を伴う業務に人は集中させる必要があります。
特に膨大な量のデータ収集や処理は、単純作業でありながら時間と労力が必要ですが、これらの作業をデジタル化することで、担当者はより高度な施策に時間を使うことができます。
データに基づいた客観的な判断ができる
マーケティングDXの推進により、定量データを根拠にした客観的判断ができるようになります。変化のスピードが早いデジタルマーケティングの世界では、判断の早さが大切です。マーケティングDXでは、蓄積したデータを活用した迅速な意思決定が可能です。
消費者の購買行動は多様化しており、購買に至るプロセスが複雑になっています。その中で担当者は経験や勘に頼るだけでなく、集積されたデータから客観的に顧客行動を分析し、オートマティックな対応ができる仕組みを整えておく必要があるのです。データ運用の幅を広げ、精度を上げることでデータの価値そのものも高まるでしょう。
顧客体験が向上する
このように、マーケティングDXによりマーケターがコア業務に集中でき、データに基づいた客観的判断ができるようになると、顧客とのコミュニケーションの質が向上します。
顧客のあらゆる情報がデータとして蓄積されていくと、顧客の行動や購買データがすべて把握できるため、例えばそのデータをもとにAIが最適な商品をレコメンドしてメールを送ることも可能です。
また、問い合わせに対する一次対応も自動でされ、顧客を待たせることもありません。DX化によって顧客ニーズや消費者行動に対応しながら変化していく力を身につけることで、企業全体としてのDXが推進されていきます。
新たなサービスやビジネスモデルの構築につながる
マーケティングDXの推進は、新たなサービスやビジネスモデルの構築にもつながるでしょう。PDCAサイクルを高速で回すことで、これまで得られなかった顧客ニーズを把握することができたり、市場や顧客ニーズの変化への迅速な対応が可能になったりします。
新たなサービスを提供するだけでなく、それに対する顧客のリアクションを検証していくことで、また新たな課題の発見につながり、さらなるビジネスチャンスを生むサイクルが実現されます。
マーケティングDX推進の課題

マーケティングDXは一朝一夕で達成されるものではありません。推進における課題を把握しておくことで導入の際のヒントにしましょう。
人材不足
マーケティングDXの推進がうまくいかない要因として、まず挙げられるのは適任者がいないことです。
マーケティングDXを推進するためには、デジタルマーケティングの知識や経験だけでなく、マーケティング活動そのものに対する深い理解が必要です。また、社内の複数の部署や関係者の理解を得ながら大きな構造改革を起こす力も必要となります。
優れたITツールを導入しても、社員が活用できなければ、マーケティングDXは進められません。 マーケティングDXの実現には、ITツールの使用セミナーを実施したり、初心者でも利用できるような使いやすいITツールを導入したりというアプローチが求められます。
マーケティング業務の複雑化
マーケティングDXにはITツールが欠かせませんが、これによって業務が複雑になるケースがあります。
例えば、これまで使用していたシステムとの互換性がないものや紐づけができないITツールを導入した場合、データ変換や加工が必要になるなど、かえって業務が複雑になり、社員の負担が増えます。
また、以前から使っていた別のシステムを継続して使用する場合、社員は複数のシステムを併用する必要があり負担が増加するでしょう。
そのため、マーケティングDX推進に当たっては業務が複雑化しないよう、既存のシステムとの相性や使いやすさを重視したうえでのITツールの選択が必要です。
既存のシステムとの互換性があるものや紐づけができるITツールの選択を行い、自動変換機能を組み込むといった対策を考えましょう。
マーケティングDXを成功させるポイント

経営層によるコミットメント
マーケティングDXの推進に重要なのは経営トップによるコミットメントです。
マーケティングDXの実現には一定額の投資が必要です。また、複数の部署を超えて改革を推進し、時には顧客や取引先とのコミュニケーションや商流を見直す必要があります。
そのため、DX実現によって得られるメリットを説明し、経営層からの理解を得なければ、マーケティングDXは実現しません。
ミッション/目的の浸透
経営層の理解とともに必要なのは、社内への周知と目的の共有です。
例えば、マーケティングDXのために新たなITツールを導入しても、社員がその意図を知らなければ、業務が複雑化されたことに対して不満がたまり、活用されないでしょう。
マーケティングDXにおける成果が出ている企業は、そうでない企業と比較し、圧倒的に「ミッション・ビジョン・バリューが定義され、浸透している状態」になっているという電通の調査結果もあります。
会社の都合の良い施策に振り回されていると社員に捉えられないためにも、「なぜやるのか」を関係者が共有し、同じ目的のもとに各自が動く必要があるでしょう。
顧客視点での顧客体験の向上
マーケティングDXは、企業側の業務効率化や生産性の向上が最終目的ではありません。それにより、より良い顧客体験を顧客にもたらすことが最終的なゴールです。
顧客の視点でマーケティング施策を見直すことで、企業側のメリットだけではなく、顧客側にもメリットがあるサービス開発・改善への取り組みが求められます。
例えば、後述するコカ・コーラの事例ではアプリを使ってこれまでにない顧客体験をユーザーに提供したことで、企業側もこれまで得られなかったデータを取得することができました。そして、取得したデータはさらに良い顧客体験を提供するためのサービス開発に活用されます。
このように、マーケティングDXの成果が出ている企業の多くが顧客視点での顧客体験向上に取り組んでいます。
外部パートナーとの連携
マーケティングDXを進めるには、適正な人材の確保や社内教育が欠かせません。高度なツールを導入したところで、使いこなすには一定の時間を要するでしょう。
そこで、外部人材の活用を検討する企業も増えています。 社内にはない経験やスキルが得られるほか、外部の視点によって新たなアイデアを取り込むきっかけにもなるでしょう。
全て自社でやるのではなく、ツール導入も含めた「パートナー企業との連携」も視野に入れることがポイントです。ミッションやゴールを共有できるパートナーと連携しながらマーケティングDXを推進することで、自社が力を入れるべき領域により時間を使えるようになるでしょう。
効率的に社内で始めることができるツールを利用
マーケティングDXを推進するためには、必ずしも専門的な知識に頼ることはありません。高度なスキルが必要ななくとも、誰でも簡単に始められるところスタートすることで小さな一歩を踏み出せるでしょう。
最も簡単なのが企業が保有する顧客データを整理し、誰もが保持している携帯電話番号を活用することです。携帯電話番号は企業のマーケティング活動で見落とされがちですが、国内や海外の調査でもSMSの開封率は80%以上と言われ、そのマーケティング効果はEメールの20倍以上となります。
CM.comが提供しているMobile Marketing Cloudを利用することで、企業は顧客にSMSとEメールを一つのプラットフォームで一斉配信することができます。配信結果はCustomer data Platform(CDP)に自動で格納されていくので、社内の担当者レベルでデータを管理できる体制を築けるようになります。。
マーケティングDXの成功事例

さまざまな業界におけるマーケティングDXの成功事例を紹介します。
江崎グリコ株式会社
江崎グリコでは、マーケティングオートメーション(MA)ツールを導入し営業手法をデジタル化させ、オンライン営業へ移行。その結果、顧客コミュニケーションの質が向上し、Webからの見込み客が2倍以上に増加、売上も約10倍以上の成果へと繋がりました。
さらに、江崎グリコはMA活用のノウハウを他のB2B事業(災害用備蓄販売)にも展開。こちらも受注率がほぼ100%という成果につながったそうです。他の事業にクロスさせることで、企業のビジネス全体の変革をもたらしたという点こそ、DX(デジタルトランスフォーメーション)と言えるでしょう。
JTB
株式会社JTBは、ナビタイムジャパン、日本マイクロソフトと共同で、インバウンド向けのアプリを開発。 このアプリには、AIチャットボットが外国人観光客に対して英語で観光情報を提供したり、外国人観光客からの問い合わせに対応したり、さらには個別にオリジナルの観光プランを作成したりする機能があります。
アプリを通じて蓄積した外国人観光客の行動データや嗜好データの活用により、顧客ニーズに即したサービスの提供、魅力的な観光プランの提案など、サービスの質向上にもつながっています。JTBではさらに、インバウンドの誘致に苦戦する自治体やインバウンドビジネスに課題を持つ企業などへのサポートにも、データを活かそうとしています。
日本コカ・コーラ
日本コカ・コーラ株式会社は、株式会社アイ・エム・ジェイの「Coke On」を導入することでマーケティングDXを成功させました。「Coke On」は、ユーザーがアプリを自販機にかざしてドリンクを購入すると、15本購入で1本無料になるサービス。IT活用によって「自販機でもスタンプが貯まって無料特典をもらえる」という顧客体験の変革を実現しました。
日本コカ・コーラの課題は自動販売機の利用データの活用でしたが、「Coke On」により、利用者データの取得に成功。顧客のタイプや購入した商品が把握できるようになり、顧客ニーズに合わせたマーケティングが可能になりました。
U.S.M.H
小売業のマーケティングDX事例として注目されているのが、マルエツなどのスーパーを展開する「U.S.M.H」(ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス)です。
U.S.M.Hは、オフライン(店舗)とオンライン(ECやアプリ)を自由に行き交う新たな顧客体験を目指し、さまざまなマーケティングDXに取り組んでいます。
例えば「Scan&Go」は、店内の商品をスマホでスキャンして購入、アプリでキャッシュレス決済できるアプリです。また、Scan&Go内にはオフラインのタッチポイントとして、ネットスーパーサービス「Online Delivery」を搭載しています。
このような取り組みは、これまでは別々の存在だったオフラインとオンラインのマーケティングを結びつけることで、新たなビジネスモデルをつくり出した事例といえます。
まとめ
マーケティングDXの本質は業務変革であり、ITツールを導入するだけで実現するものではありません。業務を変革するには、これまでのやり方や文化を変える必要があります。
目的やゴールを明確にし、従業員が一丸となって取り組むことが成功の鍵となります。マーケティングDXの本質を理解し、成功への第一歩を踏み出しましょう。
